
|

|

|
| 〜より安全な摂食・嚥下を求めて〜
|
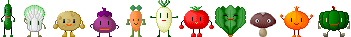
|
重度の運動障害を持つ入所児(者)は、食べたり・飲んだりすることにも、多かれ少なかれ障害を持っています。小さな頃からの口腔機能の未発達、姿勢や運動、異常筋緊張の問題などがあり、寝たままの姿勢で食事をとる場合も多くあります。このような介助は「ムセ」や「誤嚥」を引き起こし易い極めて危険な食べ方でもあります。
リハビリテーション科では出来るだけ早期から 入所者に関わり食事場面でのより安全な姿勢を考えたり、発達的問題を減らす為の口腔機能の訓練や実際に食べる場面でのより安全な食べ方の指導を行っています。
|
〜食事場面でのより安全な姿勢〜
|
| 当園では摂食時の姿勢として可能な限り座位や姿勢保持椅子を利用しています。背臥位などの食物の落ち込みやすい姿勢は誤嚥を誘発しやすく、悪い嚥下パターンを身につけることになります。座位姿勢をとることが困難な場合でも可能な限り頭頚部を起こしたより安全な姿勢の確保に努めています。
|
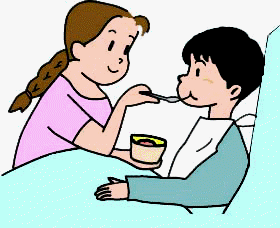 |
左の図は頭頚部の位置を正しく
自分に合った姿勢保持椅子を使用しての食事場面 |
|
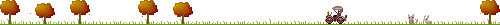
|
〜口腔機能の訓練〜
|
重症児(者)の摂食・嚥下の問題は口腔器官の形態と口腔機能の発達の問題でもあります。
対象となる入所者の口腔機能の発達レベルに合わせた訓練を早期から繰り返し行うことを通して、発達の未熟な口腔機能を向上させることが大切です。 |
 |
重症児(者)のなかには、食べ物をスプーンから口に取り込むとき、口を大きく開けすぎてしまったり、上唇で上手に食べ物を取り込むことのできない方がいます。 右の図は上唇でスプーンにある食物を上唇で取り込むことを促し、また口唇の捕食機能や口唇閉鎖機能を促す目的の訓練方法の一部を示したものです。 |
| 上唇・下唇のコントロール |
|
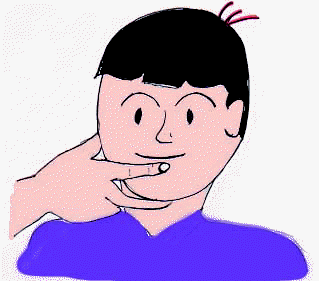 |
下顎と下唇の閉鎖性を促す目的で行う訓練方法の一部を示したもので、特に重度の方では食時の時に口を必要以上に開け(過開口)てしまう状態を多く目にします。そして口を大きく開けたまま食べ物を飲み込む ことを目にしますが、この食べ方は誤嚥を引き起こす危険性を高 いものにしてしまいます。危険な食べ方の図を参考にしてください。 |
| 下唇のコントロール |
|
| 捕食時や嚥下時に口唇や下顎の閉鎖を介助し、嚥下機能を向上させます。 |
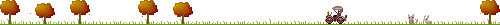
|
〜より安全な食べ方の指導〜
|
安全に食べるためには姿勢の問題や口腔機能の向上ももちろん重要ですが、それ以外にも気をつけなければならない点があります。
食事に集中できるような環境設定、食物の形態や食器 、自助具等の適合性、摂食介助では1回のスプーンの量や介助の速さ、口腔内での食物を置く位置等などについて日頃介助量の多い病棟職員に対しての指導を学習会などを通して実施しています。
|
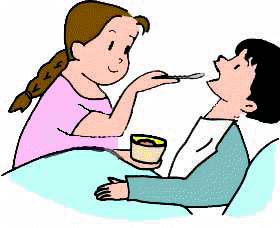 |
左の図の様に、頭頸部が反り返り且つ、口を大きく開けた状態での食事(飲み込むこと)は誤嚥という危険を伴うものです。食事は本来楽しいものですが、不適切な食べ方や介助方法は苦しみとなります。食事 は楽しく安全に食べることが出来るように心がけましょう。 |
| 危険な食べ方 |
|
| ↓ |
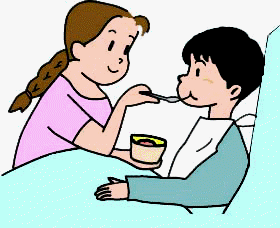 |
頭頸部が正しい位置になるように工夫(急に正しい位置に変えようとすると危険なことがありますので注意)しましょう。口は上手に閉められる様にコントロールしてあげましょう。但し、本人の口の動きが出たときは、その動きを阻害しないようにする ことが大切です。 |
| 安全な食べ方 |
|
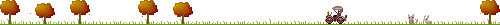
|