
|
呼吸はからだに酸素を取り込むという、私たちが生きてゆくうえで重要な役割を果たしていますが、日常生活の中で「呼吸している」ことを意識する機会はほとんどないかもしれません。それは、それだけ楽に呼吸できているということなのです。
しかし、重症児(者)のなかには、筋緊張が高いこと、胸郭の変形がみられることなどの影響を受け、空気の通りがさまたげられたり、深い呼吸ができなくなるなどの呼吸障害を持つ方が多くいます。呼吸は起きている間も寝ている間も休まず続けられるもの。呼吸が苦しいと、それだけで体にとって非常に大きな負担となってしまうのです。
そこで、療育園ではそれぞれの重症児(者)ができるだけ安楽な呼吸状態で健康な日常生活が送れることをめざし、呼吸理学療法を実施しています。
|

|

|
呼吸を安楽にするためには、空気の通り道を十分に確保することが重要です。重症児(者)は、頭部が反り返りやすい、下顎や舌が重力に負けて 落ち込んでしまうなどの様々な原因で、気道が狭くなってしまいやすいという特徴があります。とくに、背臥位(仰向け)は重力の影響を受けやすいので、側臥位・腹臥位・座位など姿勢を工夫することにより、気道を確保することが重要となります。
そこで、療育園では日常的に頻繁に姿勢をかえるよう心がける、それぞれの体に合わせた 姿勢保持具 を作成するなどの取り組みが行われています。
|
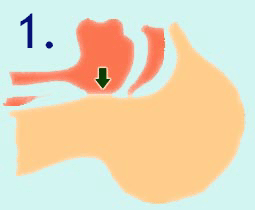 |
1.下顎や舌の落ち込みによる気道狭窄
2.下顎の前への引きだしによる気道の開通 |
|
| また、呼吸が苦しい状態が続くと、全身の緊張も高くなってしまいます。全身がリラックスしていることも、安楽な呼吸が得られる重要な要素であり、安定したポジショニングを提供したり、心身のリラクゼーションをはかることが大切です。
|

|

|
| 胸郭の動きが悪いと、十分に吸うことも吐くこともできません。胸郭の動きをよくすることはもちろん、胸郭を息を吐くときにあわせて圧迫し、十分に吐ききることを介助し、浅く早い呼吸から、深くゆったりとした呼吸ができるように手助けします。
|
|
|

|

|
| 胸郭の動きが悪いと、十分に吸うことも吐くこともできません。胸郭の動きをよくすることはもちろん、胸郭を息を吐くときにあわせて圧迫し、十分に吐ききることを介助し、浅く早い呼吸から、深くゆったりとした呼吸ができるように手助けします。
|
|
|

|