
|

|
| 拡大・代替コミュニケーション(AAC)
|
重度の重複障害をもつ人達も自分を表現したいという基本的な欲求を持っています。『自分の思いを伝えたい、誰かとコミュニケーション(意思疎通)をとりたい、そして心を通い合わせたい』。でもどうすればそれが可能になるのでしょう。
重度の運動障害のため思ったように喋ることができない、ジェスチャーもできない。口や体は動かすことはできても、思ったことをどう表現したらよいかがわからない ! ということもあります。
リハビリテーション科では、こうした入所児(者)各々の障害に合わせたコミュニケーションの方法を考え、必要な補助代替手段を創造し、コミュニケーションを可能にすることやコミュニケーションを拡大するための訓練などをおこなっています。
|
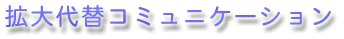
|
| (AAC) <Augmentative Alternative Communication>
|
| 拡大代替コミュニケーションとは・・・・? |
重度の表出障害を持つ人々の形態障害や能力障害を補償する臨床活動の領域を指す。多面的アプローチであり、個人のすべてのコミュニケーション能力を活用する。それには残存する発声、会話機能、ジェスチャー、サイン、エイドを使ったコミュニケーションが含まれます。
ある障害を持った場合これまではその障害をいかに克服するかが主要な課題でした。そして 、その機能の回復のための訓練を優先させてきましたが、AACの考え方はもちろんそれも行いつつ尚今ある本人の意思をも尊重し、コミュニケーションの確保も共に考えようとするものです。
|
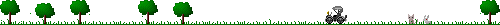
|

|
| 入所児(者)の多くは重度脳性麻痺で思ったように体を動かすことが困難です。体の粗大的な運動や体のごく一部の随意運動が出来ても、異常な筋緊張や 不随意運動などで正確に動かすことに困難さを示す人もいます。このためしゃべれても言葉がはっきりせず聞き取りにくいことや、ほとんど言葉にならない場合もあります。簡単なサインやボディランゲージのできる人もいますが、 表現語彙数が限られることから、自分の意思を十分に表すことが出来ないことも多くあります。
|
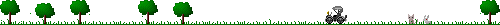
|

|
入所 児(者)によって言語面や認知面の発達レベル、さらに運動発達面から見ても出来ることは各々異なっています。またコミュニケーション能力として見た場合どんな方法で、どの程度人とやりとり出来るのかという ことも大切なことです。
これらのことを潜在能力も含め、専門的な視点からきちんと評価したうえで、入所 児(者)一人ひとりに合った表出方法やコミュニケーション方法を考えていきます。
|

カラーマッチング
|
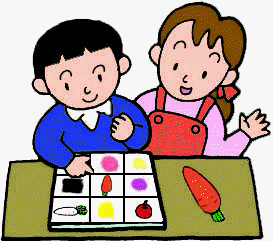
実物と絵のマッチング
|
| シンボルカードを使用してコミュニケーションの拡大を図っています。 |
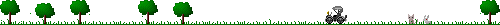
|

|
一般的によく使用され、市販されているコミュニケーションエイドとしてはシンボルブックや音声出力装置(トーキングエイド)、パソコンをベースにしたコミュニケーションエイドなどがあります。
しかし、当園の入所者がこれらの既製品をそのままの状態で使用できる場合は極めて希です。そのためパソコンを使用したコミュニケーションエイドではリハ工学部門とタイアップして個々の入所者が使用しやすいように体の動きに合わせた入力装置(スイッチディバイス)の開発を行い、さらに個々のコミュニケーションレベルに合わせたシンボルソフト、ワープロソフトの作製もおこなっています。
|
| コミュニケーションを可能にしたり拡大するための訓練 |
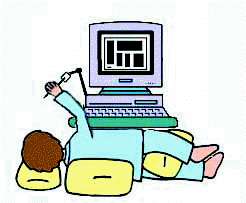
|
| 当園で作成したコミュニケーションエイドを使用して、本人専用のファイルに語彙を登録しているところです。 |
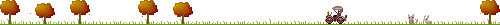
|